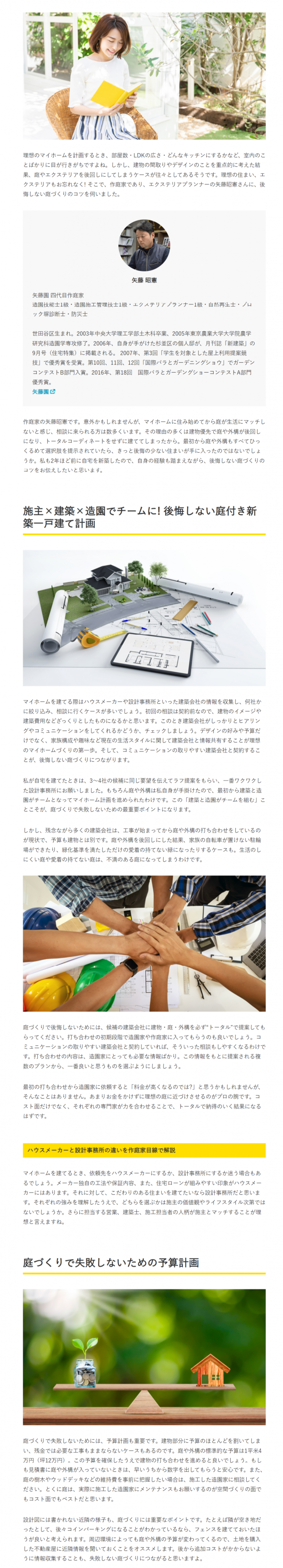庭日記
おしゃれな庭を維持するには? 庭づくりのプロが教える芝生や庭木などの手入れのコツ
庭の手入れは時間と予算のバランスが大切! 作庭家が教える庭のつくり方と管理のコツ
庭木で四季を楽しむ! 作庭家が教える一戸建ての庭づくりのポイント
後悔しない庭づくりのコツは?作庭家が考える家と庭造りの手順
アプローチ改修工事
今回は、アプローチ兼主庭の改修工事について紹介します。 改修前はただ導線上に平板が並んでいるだけで草も伸び放題で 雨の日などは、家に入る際足元を汚してしまう状態でした。 &nbs…
テラス改修工事 ~ ウッドフェンス設置でカーテンいらずのリビングに ~
リビング・ダイニングに面したテラスの改修工事のご紹介です。 施工前の写真のように、ブロック塀で囲われたテラスです。近隣の建物が高いため、既存ブロック塀の高さだけでは、 目隠しの効果がなく、せっかくの開口の広い窓もカーテン…
石張り
先日、会社の敷地内にて石張りの工事を行いました。 今回もベースの打設から仕上げまですべて自社で行いました。 車も載るのでしっかりと打ってあります。 土留め兼型枠に枕木を据え付けてあります。 千鳥に並べていってこのような仕…
現状報告
非常事態宣言を受け今回の自然再生士実地研修は残念ながら中止となってしまいました。 そこで現地の状態を少しですが報告いたします。 事前準備で実験を行った水田ですが、5%10%15%とすべての遮水層を形成した場所で水が溜まっ…
自然再生実地研修 事前準備
第8回目自然再生実地研修にむけ長泉農場にて作業を行ってきました。 今回の講習では、田んぼ作りをメインに行う予定となっているので、今回は講習に向け ・遮水層形成の実験 ・引水用の水路作成 上記2点の作業を行いました。 遮水…